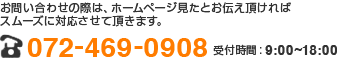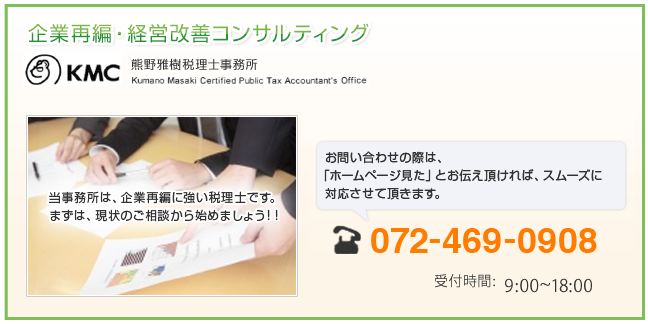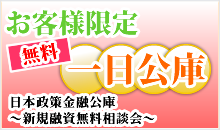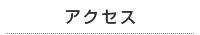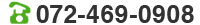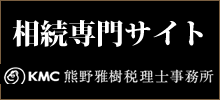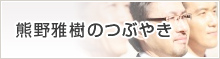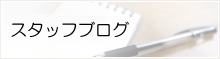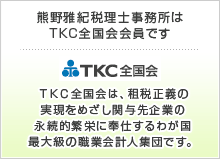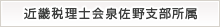相続対策
相続税(資産税)の申告から対策までサポートさせていただきます。
 相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります
相続財産の現状把握と適正な評価を行い、早い段階で相続税の試算をし、その後の遺産分割や納税資金の対策についてアドバイス致します。
相続が発生してからの対策は限られています。「争族」にならないためにも事前のご相談や対策が必要です。
相続時精算課税や事業承継支援税制などがあり、これらの相談に応じています。
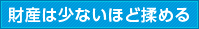
| 遺産の価額 | 調停成立件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2,002件 | 約26.8% |
| 5,000万円以下 | 3,407件 | 約45.7% |
| 1億円以下 | 1,018件 | 約13.6% |
| 5億円以下 | 557件 | 約7.4% |
| 5億円超 | 50件 | 約0.6% |
| 算定不能・不詳 | 411件 | 約5.5% |
上記より、「我が家は相続税の対象となるほどの財産はないから相続対策をする必要はない」と大多数の方が考えています。
しかし、これは大きな勘違いで、相続人の間での話し合いで遺産分割がまとまらない場合、家庭裁判所へ申し立てを行うことになります。
平成20年に家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件のうち、相続税の対象とならない人(遺産が5,000万円以下)からの申し立てが約73%を占めています。
さらに、実際は相続人が複数いる、相続税の計算上特例があるなどのケースでは、財産が1億円以下の多くの方が相続税の対象とはなりません。
その方たちも含めますと相続税の対象とならない人からの申し立て件数は約86%となっています。
相続税の対象とならない人たちで9割近くを占めているのです。
相続の申告スケジュール
 相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月 までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月 までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。
延納、物納については、申告書の提出日までに申告書類を提出しなければなりません。
相続の手続きの流れについて
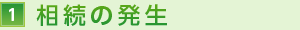

被相続人の死亡から7日以内に 死亡の届出をしなければなりません。
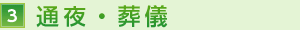
相続人が一堂に会する葬儀の際に、遺産相続について、後日改めて話し合いをしたい旨を伝え、
相続手続のことが放置されたままにならないように配慮しておきます。
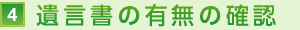
亡くなった人の遺言書があるかどうかの確認をします。遺言書の有無によって、相続手続が変わってきます。
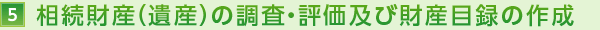
亡くなった方が使用していた貸金庫や自宅のタンス内などを詳しく調査します。相続財産(遺産)の内容・評価額を正確に把握するためにも、財産目録の作成が望ましいです。
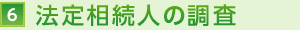
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せ、相続関係の調査をします。
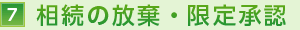
被相続人が債務を負っている場合に相続放棄又は限定承認をするには、原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
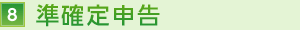
被相続人が個人事業主の場合には、死亡の日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
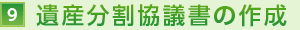
相続人の全員で遺産分割協議書を作成します。
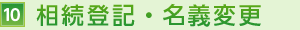
預貯金の解約手続や不動産・株式などについての名義変更手続を順に行います。
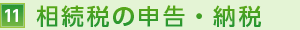
相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人死亡の日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税します。10か月の期間以内に申告しないと、高率の延滞税が課せられてしまいます。